昨日の続き。ルイスはベッドに寝たっきりだったが、大きなダブルベッドなので、家族の誰かがいつもソファよろしく
「ごろり」
と、隣で横になっている。
もちろん、イスはある。ベッドサイドに。でも、一緒にベッドに寝っ転がっている方が楽だし、何より楽しい。
おしゃべりはもちろん、タブレットで写真を見たり、音楽を聴いたり、腕や手に触れたり。
こういう
「一見、お行儀が悪そうな」
ことが、スペインではまったく「あたりまえ」なところが、日本と大きくちがうところ。
その源は
「愛する者のすぐそばにいたい」
「触れていたい」
という、純粋な思いである。
だから、お行儀が悪かろうが、それは尊い行為なのだ。だから私も三日間に渡って、ルイスと一緒にベッドに転がっておしゃべり。
「プリンセサ、最近の体の具合はどうだい?」
ドクターであるルイスは、いつも必ず尋ねる。こんな最後の時間でさえも、私の体を気づかってくれるのだ。
「大丈夫。ただ慢性の貧血があるから、たまに眠気に襲われたり疲れて横になる」
「いいサプリメントがあるから、メモして」
ルイスはしっかりとした口調で命令する。
つづりを何度もまちがえて、聞きなおす私に
「お姫さまは、書くのは苦手みたいだね」
と、笑う。それまでが、かけがえのない瞬間、思い出になっていく。
実際、私は「聞く&話す」方が「読む&書く」より得意なので、耳ばかり使っているうちに、読み書きが10倍くらい遅くなってしまったのだ。
「いいかい、鉄分のサプリメントをちゃんと飲むんだよ」
ルイスが私の腕を、ぽんぽんと叩く。
この日、ルイスは家族全員の前で
「鎮静剤を打ち始めたいこと」
「数日で意識がなくなるので、その前にやっておきたいこと」
をすべて、明確な意思で伝えた。
ふつうは高熱や肺炎や呼吸困難や、いろいろな症状が出てから死期を迎える。
でもルイスはドクターで、どういうプロセスをたどるか明確に知っていたので
「症状に苦しむ前に、意識を失くしていく」
ことを選んだ。そして、その日も自分で決めた。
私は、三年前を思い出した。べラがいよいよベッドから動けなくなって、食事も取れなくなった頃。ルイスは毎日電話をかけてきて
「今日はどんな症状だったか」
を、細かく聞くのだった。
それは私に代わって、ドクターとして「最期の時」を見極めようとする思いやりだったのだ、と今になってわかる。
ある日、ルイスは電話の向こうでぽつりと言った。
「プリンセサ、最期の時が来たよ。覚悟をしなさい」
もちろん、私は心の準備などできていなかった。薬でできることなら、何日でも生きていてほしかった。
すると、ルイスは穏やかな口調で言うのだった。
「それは、いいかい。君のエゴだ。べラのことを考えてあげなさい」
「・・・・・」
それでも、私は「嫌だ」と言い続けた。すると、今度は厳しい口調で言うのだった。
「これは友達として、医者として言う。これ以上、僕の大切な親友の苦痛を長引かせるわけにはいかない。それにどんな意味がある?」
「今日で終わりだ。プリンセサ。鎮静剤の用意をしたいと、すぐに医者に伝えなさい」
それでも受話器を握りしめて泣いている私に、今度は限りない優しさを込めて言うのだった。
「いいかい。それが、君がしてあげられる最後のことなんだよ」
誰が、こんなことを言ってくれるだろう。今になって、ルイスの思いがわかる。深い愛情が。
そして。自分の最期を、潔く明確な意思を持って決めていくルイスの姿を見ながら
「こういう終わり方もあるのだ」
ということを、ルイスは身を持って教えてくれているのだ、と思った。
(明日に続く)
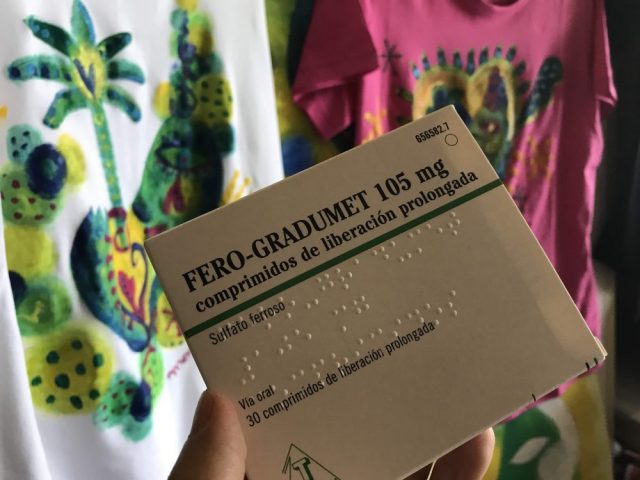
しっかり今を生きなくては それは使命だ というような気持ちにさせられます。とにかく涙が落ちます。
Sさんのように思ってくれる人がいて、ルイスも喜んでいると思います。
けして悲しいだけではない。
「人生を最後まで選び取る」ことを、身を持って教えてくれました。