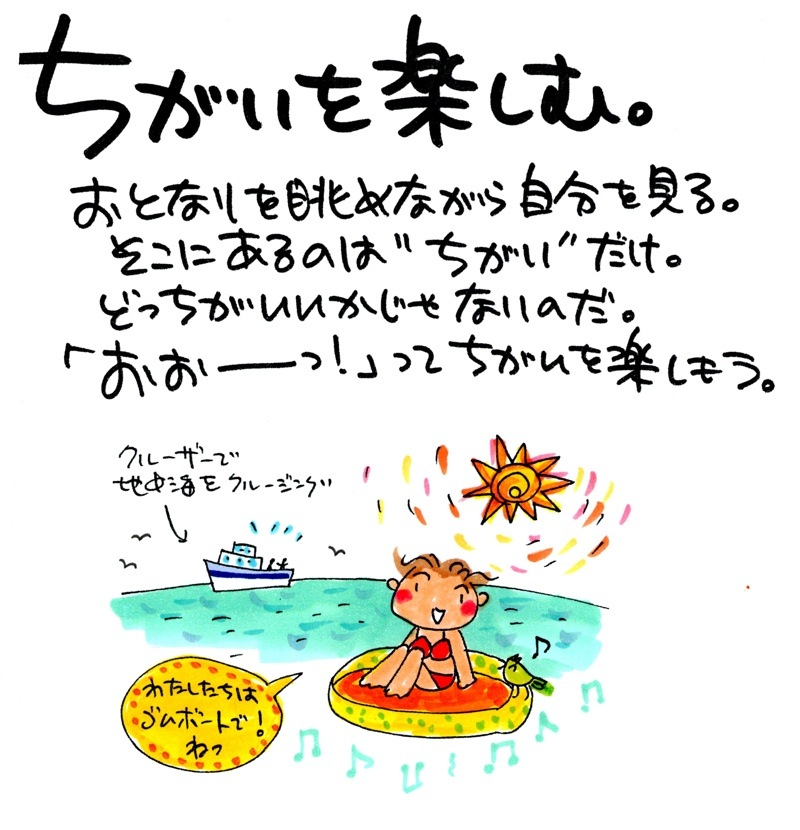セビージャ・タンゴ・フェスティバルが終り、ほっとしていると
知り合いの音楽関係者から電話が入った。
「ケンピンスキーホテルでプライベートパーティがあるんだけど空いてる?
明後日、夕方6時。詳しいことはホテルで聞いて」
いつもながらすごいと思うのは、こうして
電話してくる人たちが決して現場には現れないことだ。
つまり、何が起っても
「あとは自分たちで何とかやって」
ということを暗に意味する。う──ん。
マラガから車で1時間。エステポナにある5つ星ケンピンスキーホテルへ
機材とともに駆けつける。ところがレセプションの方
「今日はどこのレストランにもプライベートパーティの予定は入っていませんねぇ」
と首をひねっている。そんなはずはない、ともう一度
確認を取ってもらうと
「あっ、それはスイートルームのお客様のことですね」
と、いままでのぐだぐだが嘘のように速やかに
機材と共に最上階のスイートへと案内された。
「こちらです」ってドアが開くと
部屋の真ん中のソファにゆったりと沈み込んで手招きしているのは、
どうみてもまだ20代後半の若者ではないか。
プライベートディナーはそのスイートの宿泊客の“二人のロシア人”のためのものだった。
さっそくリビングの隅に機材を運び込ませていただき演奏を始める。
「シャワーを浴びるので何か弾いてもらえる?」
一瞬、耳を疑った。ベラも同じだったと思う。
「シャワーって言った?」
と不安げに確かめる。
「やっぱ、さっぱりした曲がいいのかな」
って関係ないと思うが私たちは目の前に居ない“シャワーを浴びるロシア人”に
捧げる曲を弾き始めた。
その後のディナーはスイートにくっついている大きなテラスで行われた。
10m四方のテラスの中央に置かれた花だらけのテーブル。
その4、5m横に私たち。
二人のボーイが付きっ切りで給仕をしている。
庶民の私など、こんな他人の方が多いところでくつろぐのが既に無理だけど、
お金持ちの方々の感覚は違うらしい。自分の家族より他人の方が
多い中であたりまえにプライベートが進行していく。
「ご用意ができました」
とボーイがロシア男の耳元にそっとつぶやく。
するとロシア男おもむろに立ち上がり
その一角に用意されたバーベキューコーナーに近寄ると
「えいっ!」
とばかりに肉をひっくり返した。
数回、そのひっくり返しが続くと今度はその肉を
ゆったりとした足取りで彼女(奥さんではないと皆暗黙の了解)の
皿に置いた。
「僕が焼いたんだよ」と言わんばかりに。
「ひや──っ」これが金持ちのバーベキューなんだ。
あまりの別世界ぶりに腰がなえそうだったが
まさかその後にもっとすごいことが待っているとは
思っても見なかった。
(第34話につづく)